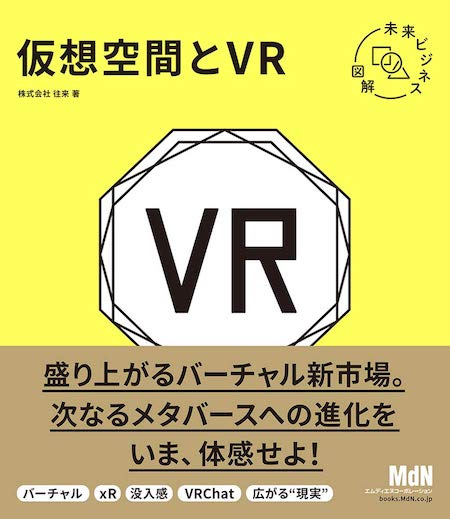久しぶりのライフハック・ジャーナルをお届けします。Lifehacking.jp の堀です。
後述しますが、この二ヶ月ほどはとある本の作業に忙殺されていてさまざまなものの更新が滞っていたのですが、ようやく時間がつくれるようになってきましたのでいつもどおりのアウトプットに戻ろうと思っています。
そろそろ新型コロナウィルスの蔓延にともなう最初の緊急事態宣言から一年が経とうとしていますが、いまも自分のなかで緊張が解けない部分と、どこかで麻痺してしまった部分とが混じり合って、奇妙な日常を形成しています。
去年、私は恐れすぎることによってどこかで判断が「反転」してしまい、「こんなに大変なはずはない」「自分は大丈夫なはず」と自分で自分を非科学的に説得してしまう心理について書きましたが、私自身がそうした誘惑に負けつつあるように感じる日もありました。
知り合いに比較的重い感染のケースが発生してようやく、現実は去年からなにひとつ変わっているわけではないことを、変わっているのはそれに対する自分の態度だと認識することができたほどです。
一年前に比べてさまざまな対策や行動の変化が根付いてはいるものの、もうしばらくは、心のなかに生まれそうになる正常性バイアスに抵抗できればと思っています。
では今回の話題にいきましょう。
コラム:メタバースというフロンティア
ここしばらく忙しくしていたのは、チームで執筆しているとある本の制作に自由時間のほとんどをとられていたからなのですが、その本がようやく3月25日に発売されることになりました。
題名は「仮想空間とVR」で、バーチャルリアリティと、そのなかで誕生しつつあるメタバースが話題になっています。
私はVRが専門というわけではありませんし、参加した著者の誰もがVRを生業にしているわけではありません。VRの経験もまだ数年といった程度ですので、この分野を切り開いてきた先人に比べればひよっこですし、いまこの世界で活躍しているガチ勢の人々に比べれば知識も経験も不足しているはずです。
それでも今回、本書を書くに至ったのはまさにいまそうした「ガチ勢」の人々と「初心者」とをつなぐための扉となるための本のニーズが高まっていたからです。かつてiPhoneがそうであったように、VRがわれわれの生活を根底から変えてしまう可能性をもった技術だと確信しているからこそ、このタイミングでそうした本を書かせていただけるのは幸運だと感じています。
本書は、通常VRときくとすぐに連想させるようなゲームやエンターテイメントの利用、あるいは教育、建築現場での応用といった、既存のビジネス利用の最前線にもふれつつも、後半はVRChatを軸とした「メタバース」について大きくページを割いているのが特徴です。
「メタバース」は1992年にニール・スティーヴンスンが小説「スノウ・クラッシュ」で作った造語です。かれはここで複数の仮想空間がつながり、ひとびとがそこで生活できる巨大なバーチャル空間としてそれを構想しており、このイメージはのちに「サマー・ウォーズ」のOzや、「Ready Player One」のOasis、「ソードアート・オンライン」にも活かされています。
メタバースの定義はそのどんな側面を強調したいかによって揺れ動きますが、多くの場合は仮想空間内に自分と他者が存在し、そこで経済活動や社会活動を営めることとされています。メタバース的といわれているサービスには「Second Life」が筆頭に挙げられますが、「ウルティマオンライン」にも「ファイナルファンタジー XVI」にも「あつまれ どうぶつの森」にもある程度のメタバースらしい側面は存在します。
そしていま、もっともメタバース的なものに近いサービスとしてVRChatが存在します。何万もの仮想世界で大勢のユーザーが思い思いの姿で楽しんでおり、ここでしか出会うことができない仲間やコミュニティが存在しています。しかしスマートフォンやブラウザからアクセスできる「表」のインターネットからは見えにくいために、そうした場所があることを知らなかったという人も多いかもしれません。
たとえば、VRChatにはすでにそこで活動をしている劇団や、ダンスの専門家、カメラマン、店といったものが存在します。劇団ならば舞台となる世界を自分で設計し、俳優のアバターも作成した上で、脚本、カメラワーク、演出といったものもすべてユーザーが自分で制作します。店ならば店舗の空間、ウェイターのアバターといったものを用意して客を迎えます。
そのすべてに共通しているのは、向こう側に本物の人間がいるという点です。仮想空間のなかに自分がいて、他者がいて、時間を共有している感覚が独特の面白さを生んでいるのです。
現象学的社会学の名著である「生活世界の構造」でアルフレッド・シュッツとトーマス・ルックマンは、自分がそこにいること、他者がそこにいること、相手が自分と同じ意識をもって世界を認識しているという前提が「生活世界」であると規定して、そこからさまざまな社会的現実が生まれることについて考察しましたが、もしシュッツがVRChatを体験していたならばいったいなんと言っただろうかと興味がわきます。
ヘッドマウントディスプレイで視覚と聴覚を共通の仮想空間におきかえて、お互いの存在をデジタルなアバターで指し示すだけで、そこに社会的な空間が発生するというのがメタバースの魅力ですし、プラットフォームとしての先進性といえます。
本書は入門書ですので、そうした込み入った議論をするところまではページ数がなかったのですが、それでもVRがメタバース化してゆくにつれてどんな法的・倫理的な議論が生じうるのか、どんな新しい経済活動が生まれるのか、どんな新しい職業が生まれるのかといった話には触れています。
VRはiPhoneのように社会を一変させる力をもっている。この一行にまだ納得がいかない、不審感をもっているひとも多いと思いますが、そんな人にこそ読んでほしい一冊に仕上がりましたので、ぜひ手にとっていただけると嬉しいです。
コラム:アーカイブされないコンテンツ。Clubhouseと、ブログ
音声でつながるSNS、Clubhouseの人気が爆発して一ヶ月半、ようやくその過熱ぶりがいったん収束しつつあります。
わたしも最初の10日間ほどは朝も晩もひっきりなしにClubhouseのルームに出入りしてさまざまな人とおしゃべりを楽しんでいましたが、最近は利用の仕方も落ち着いてきました。
そしてあらためてClubhouseについて考えると、ここ数年言われていた、パーマリンクの存在しない、アーカイブが意味をもたないコンテンツの台頭について思い起こさずにはいられません。それは間接的にブログといった、アーカイブ性を基調としたメディアを骨抜きにしているといってもいいのです。
Clubhouseが活性化している時間
ブログであれ、読書であれ、SNSといった時間の使い方であれ、それがどのような時間を「活性化」しているのかと考えるのは有益です。
たとえばツイッターはこれまで誰も発信することを考えていなかった個人的な思考や、日常の瞬間を世界中のユーザーにシェアすることを可能にしました。ツイッターを長い論考のために使う人もいますが、大半のひとは日常の数秒から数十秒の時間を消費してつぶやき、他者のつぶやきを消費しています。活性化している時間はちょっとしたスキマ時間であったり、移動時間であったり、別のメディアを視聴しているときの片手間の時間といえるでしょう。
ブログを読んだり書いたりする時間はツイッターに比べればもう少し長めで、熟考的で、読む側にとっても相対的にハードルが高めです。ツイッターのタイムラインをながめていて、元記事を読むことなくタイトルだけでRTするひとがとても多いことを考えると、いかにブログやウェブメディアが「重く」なってしまったかがわかると思います。
ではClubhouseは? というと、実はツイッターよりも軽いうえにアーカイブも残らないという意味において、とても注意しなければいけません。
Clubhouseのルームはあっという間に友人やフォロワーを集めて会話ができるのでとても楽しいですし有意義にもみえるのですが、雑談に使うつもりがなかった時間を膨大に消費してしまいますし、しかもそのルームは放送終了後に消えてしまいますのでアーカイブ性もありません。
Clubhouseはこれまで利用不可能だった時間を活性化しているのではなく、むしろこれまで仲間とのおしゃべりに使えなかったために別のことをしていた時間を消費して対話に振り向けているという特徴をもっているのです。
長文をよむコストがさらに高くなる
ではClubhouseに意味がないかというともちろんそんなことはありません。対話によって新しい視点を得ることもできますし、通常ならばブッキングできない人同士の貴重な話題を聞くことができるチャンスが増えているのは有益です。
しかし、それが本質的にはテレビCMをみているのと同じ体験であることはどこかで注意しておく必要があります。テレビCMはテレビ番組そのものに比べると引用がしづらく、いかに面白かったり内容があったとしても流れ去って消えてゆく性質をもった情報です(最近だとたいていのCMはYouTubeでみることができますので、そういった場合は除きますが)。
Clubhouseのルームも、いかに面白くても引用不能ですし、その学びは放っておくとルームが閉じると同時に消えてしまうものです。
しかもClubhouseが活性化している時間はよりアーカイブ性の高い活動、たとえば読書やブロクの執筆や購読といった時間を消費する形になりがちです。「いま、この人とどうしても話したい」という気持ちが叶えられるのは尊いですが、他のことをする時間とのバランスの上で評価しなければいけないでしょう。
とはいえ、時代はむしろこうしたリアルタイムの、アーカイブ性のない、人と人との対話やFOMO(自分だけのけものにされていないかという恐怖)を煽って時間を消費するメディアが増える方向に向かっています。一見、価値のある対話や出会いが増えているようにみえますが、それはすでに人脈や肩書やキャリアといった、なんらかのソーシャル資本をもっている人に有利に働きがちです。
そしてその背後で、長文のブログや本を読むといった時間の使い方は削ぎ落とされがちです。その価値が目減りしているわけではないのですが、リアルタイムで実行できる価値のある活動が増えたために相対的にそれを選ぶときのコストが増えているといっていいでしょう。
実はClubhouseのようなメディアにはツイッターのようなSNSも骨抜きにしてしまい、ルームが開いたときの通知のためにしか利用されない土管のような存在にしてしまう潜在的な可能性があります。だからこそ、ツイッターはClubhouseを真似たような機能であるSpacesを開発中ですし、Facebookも同様の機能を開発中だとリークされているくらいです。
私はここで、Clubhouseよりも読書やブログの執筆といった活動のほうが価値があると断定したいわけでもなければ、Clubhouseなどのリアルタイムメディアの活用を避けるべきといいたいわけでもありません。
しかし時間の使い方のとある選択が、単に他の選択肢を選ばなかったというのにとどまらない、時間に対する価値観の変化を生み出していることに注意したいと思うのです。
News:最近のコンテンツ
ブログの手が止まっている間も必ず毎週更新していたのが「ライフハックLiveshow」でしたが、個々最近世間を騒がせているNFT(Non-Fungible Token)の話題について時間をかけて触れたのがこちらの回です。
近いうちにまたブロガーのゲストをお迎えして、Clubhouse時代のブログみたいなテーマについて触れることができればと思っています。
Sharing:面白かったツイート
今回は一つだけご紹介。「ときとして、パパであることが本当に上手なひともいるのだ…」というこのツイート。
みているだけで楽しくなってきますね。
それではまた来週!